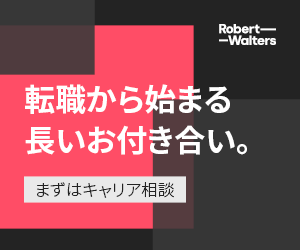経理の仕事を行なっていると、会計監査、税務調査、内部監査など様々な監査を経験することになります。このような監査に対して、どのように対応すべきか本日は記事を記載します。
監査の目的とは
監査の目的については以前の記事で記載しましたが、主な目的は社内に不正がないことの調査となります。監査人がすでに実行された業務を再度見直し、対象期間に不正がなされなかったのかを再度確認するのです。
しかし、近年はそれにとどまらず、業務の妥当性や効率性、不正が起こりにくいような内部統制の仕組みが構築されているのかも監査の対象となってきています。既に実行された業務に法律や規律上の問題があるのかを調べるだけではなく、企業経営という大きな観点で意見を述べるケースが増えているのです。
監査対応について
では、このような監査に対してどのように対応することが望ましいのでしょうか。
よくある監査対応は指摘を防ごうというもの
よくある監査対応は監査による指摘を極力防ごうというものです。監査対象や監査時間を最小限にとどめ、指摘の起こりそうな業務には話が及ばないように事前に対応を協議します。
このような考えで監査対応をしている会社は、下記のような監査対応方針を採ります。
【よくある監査対応方針】
・弱点のある業務が監査対象に当たらないように、監査人を誘導する
・監査対象に当たった業務に関して、必要最小限の書類のみ提出する
・監査の書類の提出を可能な限り遅らせ、監査人の実地監査時間を減らす
・監査対象事項について、事前に関係者一致の回答案を作成し、監査に臨む
監査人を敵とみなし、極力、敵に情報や時間を与えず、指摘を防ごうというのがこの考えにおける監査対応方針になります。
内部監査の場合、本社から出張して来た監査人を連日、飲み会に連れて行き、定時後に仕事ができないようにし、また現場の苦境を伝え、指摘をしにくくするというのもよくある方法の一つでした。
この監査対応方針は理想的なのか
では、この監査人に情報や監査時間を与えず、指摘を防ごうという監査対応方針は理想的なのでしょうか。
監査の指摘を防ぐという観点ではあるべき対応
監査での指摘を防ぐという観点では、このような監査対応方針は効果のあるものとなります。監査対象が多ければ多いほど、監査時間が長ければ長いほど指摘される確率は高まるため、この監査対応方針を実施することで指摘される確率は極力小さくなると言えます。
一方で、気付きにくいリスクや課題もある
しかしながら、このような監査対応方針にはリスクや課題もあるのです。有料記事ではどのようなリスクや課題があるのかと理想的な監査対応方針はどのようなものであるのかを記載したています。
監査は健康診断と似ている
監査は健康診断のようなものです。健康診断に行って、医師に健康な部分だけを見せ、健康であるように振る舞い、医師に健康であるというお墨付きをもらうような監査対応をしていないでしょうか。
既に悪い部分があれば、大病になる前に指摘してもらう、悪い生活習慣があれば、改善できるように助言をもらい、健康な体質を維持できるような対応を行うべきなのです。
監査を行うにもコストがかかります。監査人を敵ではなく味方と考え、監査を活用しながら、企業体質の強化する監査対応方針をおすすめします。
記事の続きはこちら